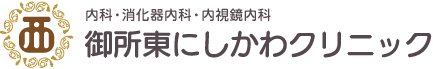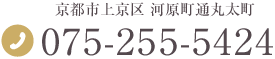新着情報News
健康トピックス
がんのリスクと定期的ながん検診
2023年05月05日
皆さま、こんにちは
GWいかがお過ごしでしょうか。クリニックでは、連休中に発熱患者さまへの診察対応をおこなっておりましたが、コロナ感染の大きな拡大もみられませんでした。5月8日より、いよいよ新型コロナ感染症も5類へ引き下げとなり、行政機関や医療機関の対応も変更され、私たちの生活もがらりと変わることになりそうです。
ここ数年のコロナ感染拡大により影響があったものとして、がん検診の受診率の低下があげられ、2019年から2021年にかけて受診率が10%程度減少していることが報告されています。胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5つのがんは検診を受けることで早期発見でき、死亡率が低下することが科学的に証明されています。がんは早期に発見できれば治る可能性が高く、発見が遅れるほど治療は難しくなりますので、がん検診を受けることはがんから命を守ることにつながるといえます。
一方で、がんになりやすい要因についても近年さまざまなものが明らかにされています。国立がん研究センターがん予防・検診研究センターがまとめた「がんを防ぐための新12か条」のうち、日常生活との関係が深いものとして、喫煙、飲酒、食事(脂肪や塩分の過剰や野菜不足)、運動不足、体格(肥満、やせすぎ)、感染(肝炎ウイルス、ヘリコバクター・ピロリなど)などがあげられます。がんを確実に予防できる方法はまだありませんが、普段の生活や自身の状態をチェックして上記の生活習慣を見直すことで、発症リスクを下げることはできます。
当院では、がんの予防のための生活習慣の改善指導を日頃より力をいれておこなっておりますが、気になる症状があった場合の早期受診や定期的な検診による早期発見も同時に大変重要ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
風疹の症状と抗体検査
2023年04月15日
皆さま、こんにちは
4月に入り、風疹検査のクーポンを持参される患者さまが増えてきましたので、今回は風疹についての話題です。
風疹は風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症で、軽症のものから高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認める場合もあります。とくに、成人が感染した場合には小児の症例よりも重篤となることが多く、感染歴のない大人は注意が必要です。また妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きる(先天性風しん症候群)可能性が高くなります。風しんウイルス感染を予防するのには、ワクチン接種が最も有効ですが、昭和37年度~昭和53年度生まれの男性では過去に公的に予防接種が行われていなかった経緯があります。そこで、これらの年代の男性には現在自治体から、原則無料で風しんの抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券をお送りしています。多くのかたが抗体検査を受け、必要な予防接種を受けていただくことで、風しんの流行はなくなると考えられています。
あなた自身の健康と、これから生まれてくる子どもたちを守るために、ぜひ風しん抗体検査と予防接種にご協力ください。
苦痛の少ない内視鏡検査と鎮静剤
2023年04月02日
皆さま、こんにちは
桜が満開の季節となり、京都も国内外の観光客がふえてきましたね。
当院でも、海外からの内視鏡検査を希望するかたがふえており、本日は苦痛の少ない内視鏡検査の話題です。
胃カメラでは、内視鏡を挿入する際にスコープがのどの奥に触れると反射によって吐き気や嘔吐(おうと)といった苦痛がみられます。一般には局所の麻酔薬をのど周囲にスプレーすることで、のどの感覚をおさえて嘔吐反射をやわらげます。しかし、もともと反射のつよい方や緊張・不安のある方は、それでもなお苦痛を感じることがあります。
大腸内視鏡検査では、内視鏡を挿入する際に大腸を伸ばしたり、大腸の中を広げてみるために空気を入れすぎると、お腹がはったり、痛みがでます。特に普段から便秘のある腸の長いかた、おなかの手術歴で腸の癒着のあるかたで、そのような症状がみられやすいです。
このような場合に鎮静薬などを注射することにより、意識を低下させて緊張をやわらげることで、苦痛を軽くすることができます。鎮静薬の投与量は、呼びかけに反応する程度の量に調整(意識下鎮静)しますが、ひとによっては血圧が下がったり、呼吸が弱くなることがありますので、検査中と検査後も意識がはっきりするまではモニターをつけて監視し、薬の効果がきれるまで院内で休んでいただきます。また検査が終わった後も、その日1日は自動車やバイク、自転車の運転を控えていただきます。
一方、鎮静薬を使用しなくても、医師の技量とともに医師と患者さんとの信頼関係によって検査に伴う苦痛がやわらぐこともしばしばみられます。当院では細い径の内視鏡を導入しており、鼻から挿入する経鼻内視鏡を施行することによって苦痛がやわらぎ、鎮静薬を使用しなくても検査を楽に受けることも可能となっています。
最近では「苦痛のない内視鏡」を望まれる患者さんが多くみうけられます。内視鏡検査は病気の診断のために受けて頂くものであり、検査も一回限りではなく、繰り返し受けていただくことも多いため、検査が楽に受けられることはベストな内視鏡診断につながり、患者さまへの恩恵も大きくなると考えます。
当院では、ひとりひとりの患者さまにあわせて、内視鏡検査の不安やストレスと検査による苦痛や不快感をなるべくやわらげることをモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
ワクチンの効果について
2023年03月19日
皆さま、こんにちは
今回は、新型コロナワクチンの公費接種が始まって以降、私たちの生活により身近な存在となったワクチンの話題についてです。
ワクチンは、細菌やウイルスなどの病原体によって引き起こされる、さまざまな感染症への対策として現在使用されています。”ワクチンて効くんですか?”と質問される方もおられますので、まずはワクチンが効果を発揮するメカニズムからおはなしします。
ヒトのからだには、一度病原体が入ってくると、その病原体を覚えて再び体の中に入ってきても病気にならないようにするしくみである”免疫”があります。ワクチンは、病原体の毒性を弱めたり無毒化にしたもの接種することにより、通常の感染(自然感染)のように実際にその病気を発症させるわけではなく、体の中に免疫のみを誘導することにより病原体と戦える準備をつくるのに役立ちます。その効果は、感染症の発症を予防したり、発症後の重症化を少なくして、重症の最たるものである死亡を少なくするなどの効果が期待されます。
乳幼児期は病気に対する抵抗力が十分に発達しておらず、また高齢になると記憶していた免疫力が徐々に低下し、病原体の種類によっては非常に重い症状や後遺症を引き起こすものもあります。健康だとなかなか実感するのは難しいワクチンの効果ですが、感染症から健康と命を守る方法として、最も安全でかつ確実な手段であるといわれています。
当院では開院以来、地域の皆さまの健康増進の一環として、新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンなどの接種を提供してまいりました。最近では、帯状疱疹ワクチン、肺炎球菌ワクチン、さらには4月より公費接種が開始される9価子宮頸がんワクチン(シルガード9)などの問い合わせが増えており、皆さまに安心してワクチン接種を受けていただけるシステムづくりに励んでおります。ワクチンの種類に応じて接種時期や効果が異なりますので、ご相談などございましたら、いつでもお気軽にご連絡お待ちしております。
急な胃の痛みとアニサキス症
2023年03月05日
皆さま、こんにちは
3月にはいって少しずつ暖かくなり春らしさが感じられる頃合いとなりました。
開業依頼、急な腹痛でのご相談もふえてきましたので、今回はアニサキスの話題です。
「アニサキス」とは、海洋生物に寄生する寄生虫のことで、これらが寄生した生鮮魚介類を生で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に侵入することで強い腹痛や吐き気、蕁麻疹などのアレルギー症状を引き起こします。サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジなどの魚介類に多く寄生し、加熱または冷凍により死滅しますが、下処理のない新鮮な刺身やお寿司などを食べると発症することが多いです。食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐を生じますので、食べたものに思いあたるものがあって受診される患者さまがほとんどです。まずはしっかりと問診を行って、症状の原因を選別することが重要となります。胃アニサキス症が疑われる場合には、迅速に胃カメラ検査を実施し、アニサキス虫体が確認できた場合はその場で摘出を行うと、速やかに症状が改善します。万が一摘出できなかった場合でも、アニサキスは1週間程度で体内で死滅しますが、まれに消化管穿孔や腹膜炎になることがありますので、慎重に経過をみながら対症療法での治療が必要となります。
当院では、胃カメラ・大腸カメラなどの内視鏡診断、超音波検査での画像診断により、さまざまなおなかの症状に対して適切に対応できるように注力しております。最後に食事をとられてから8時間程度経過していれば、当日中に胃カメラでの迅速診断も可能ですので、急なおなかの症状でお困りの場合はお気軽に御相談ください。
動脈硬化と頸動脈エコー
2023年02月19日
皆さま、こんにちは
今回は、動脈硬化の話題です。2月にはいり、4月からの入職に向けて健康診断を受けられ方がふえてきましたが、検診結果のご相談で来院される方も多くなっております。なかでも血糖値、コレステロールや血圧の上昇を指摘されての相談が増えている印象です。これらを放置した場合の一番の問題は、動脈の壁が硬くなる動脈硬化です。
本来、動脈の壁は弾力性がありますが、年齢や生活習慣が原因で血管の内側にコレステロールや線維など、プラークがたまると血管が狭くなったり、弾力がなくなったりします。やがて血栓ができて血管につまってしまうと、心筋梗塞や脳梗塞の発症につながります。高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満などがあると、血管への負担が慢性的にふえて、本来の加齢に伴う変化以上に動脈硬化をすすめてしまいます。
動脈硬化の程度を調べる検査はいくつかありますが、最も簡単に評価できる方法として、頸動脈(けいどうみゃく)エコーあります。頸動脈は脳に血液を送る大切な血管で、エコーで血管壁の厚さと血管の内側の状態(細くなっていないか)を画像観察することで、その場で迅速に判断することができます。腹部のエコー検査と異なり、飲食の制限などが不要で、しっかりと首がでる検査しやすい格好で来ていただくだけで問題ありません。
年齢問わず、身体に悪い生活を送っている場合や健診結果が気になる方は、大きな病気を発症する前に一度頸動脈エコー検査を受けてみませんか。検査をきっかけに、生活習慣の見直しや健康意識の改善につながるかもしれません。
長びく咳でお困りの方
2023年02月05日
皆さま、こんにちは
先日は全国的な大寒波で、転倒事故が多く見受けられました。
当院の前にも大雪が積もりましたが、スタッフ一丸で除雪作業を頑張り、幸いにも大きな事故もなく過ごせました。あらためて協力いただいた皆さまに感謝です。
さて、今回は咳の話題です。新型コロナおよびインフルエンザ感染症の流行に伴い、長びく咳で来院される患者さまが増えてきております。多くは感冒後咳嗽と呼ばれる感染の後遺症によるものですが、なかにはアレルギー体質や喘息の前駆症状で咳が続いていたり、肺に重大な病気が併存していたりすることがあります。さらには感染後の影響で喉の知覚が過敏になっていたり、胃酸の逆流が症状の誘因になっているケースも少なからず存在します。感染から2週間以上にわたって咳が残存する場合は、聴診での診察にくわえて、アレルギーチェックの血液検査、胸のレントゲン検査、場合によっては胃カメラ検査などで原因をつきとめていくことが必要になることがあります。それぞれ咳が続く原因によって治療法が変わりますので、長びく咳症状にお悩みの場合はぜひご相談ください。
肥満と運動習慣
2023年01月15日
皆さま、こんにちは
本日は、毎年恒例の全国都道府県対抗女子駅伝です。市内の主要道路を多くの女性ランナーが駆け抜けるたすきリレーで、今年で41回目の大会となります。
クリニック前の丸太町通りがちょうど7区→8区の中継地となっており、終盤の大きな盛り上がりとなるスポットで、大変楽しみにしております。
そこで今回は、運動に関わる話題です。肥満改善の相談で受診される方には、必ずお話しさせていただいておりますが、肥満の2大原因は、食べすぎと運動不足です。定期的な運動習慣をもつのが難しいかたも多いですが、過剰なカロリー摂取で溜め込んだ内臓脂肪を消費するのには、運動は欠かせない要素となります。運動の種類には有酸素運動とレジスタンス運動の2種類がありますが、脂肪の燃焼には有酸素運動が有効で、食後から少し時間をおいた小腹が空いた時間帯に少し息が上がる程度の運動を10分以上(できれば30分程度)継続できると効果が期待できます。ウォーキングや軽めのジョギング、プールでの運動、エアロバイクなどが適したこれらに適した運動です。現代人が慢性的な運動不足になっている最大の原因は、交通手段の利便性が向上し、歩く量が減ったことが一因とされています。コロナ禍で在宅勤務が増えたことにより、この傾向がさらに顕著になっている印象です。駅伝観戦であがったモチベーションを忘れないうちに、手軽にできるウォーキングなどから始めてみませんか。
胸やけと胃もたれの症状
2022年12月18日
皆さま、こんにちは
今年の冬も一段と寒さが厳しい時期になってきましたが、体調おかわりなくお過ごしでしょうか。
今回は、胸やけと胃もたれの話題です。これらの症状でのご相談は病院勤務の時代から多かったのですが、クリニックでの外来では益々増えております。原因としては、逆流性食道炎,消化性潰瘍,癌などの器質的な異常をまず否定しなくてはいけないので、胃カメラ検査での確認が最初に必要になります。しかしながら検診や他院の胃カメラ検査で、すでに異常なしと診断されたものの、やっぱり症状がすぐれないとのことで当院を受診される方も多くおられます。
消化管に内視鏡でみてわかる異常がないにもかかわらず、これらの消化器症状が慢性的に存在する場合を、機能性消化管障害と呼び、症状や機能障害の部位に応じて、機能性ディスペプシア、機能性胸やけ、過敏性腸症候群などと診断されます。これらは食事内容、飲酒習慣、睡眠状態、ストレス状況などの様々な因子が誘因となって腸内細菌叢の異常、粘膜の免疫機構、内臓の知覚過敏、中枢神経系の調節異常など複雑なメカニズムを介して発生するため、複数の病型が合併することも多いです。時代の流れに伴いピロリ菌の感染者が減る一方で、生活習慣の多様化やストレス社会の中で、確実に増えている疾患であります。
症状の改善やコントロールがすんなりとはいかず、時間がかかる場合もあり、奥が深い領域であると実感しておりますが、患者さまの症状をしっかり確認しながら最適な薬剤の組み合わせを見つけていくのが最善と考えております。時間がかかる作業ではありますが、あきらめずに一緒に頑張りましょう。
肝機能の異常と本当はこわい脂肪肝
2022年12月04日
皆さま、こんにちは
クリニックも開院して1ケ月が過ぎ、多くの患者さまに来院いただきましてスタッフ一同大変やりがいを感じております。
ご来院の相談の中で、本日は私の専門分野である肝臓検査での機能異常についての話題です。
肝機能に異常をおこす原因は、B型肝炎、C型肝炎などの肝炎ウイルス、免疫異常の肝障害、薬の副作用、お酒の飲みすぎなど多岐にわたりますが、栄養状態の偏りによる脂肪肝の割合が近年増えております。肝臓に脂肪が過剰にたまった”脂肪肝”は、多くの場合で肥満が背景にあるため、健診などの結果を全体的に見わたすと診断が比較的容易ですが、一部では肥満のない脂肪肝(non-obese /lean NAFLD)が存在します。肥満の基準は満たさない脂肪肝としては、体重の中での内臓脂肪の割合が多い”かくれ肥満”、脂肪組織に脂肪を十分貯めることができない脂肪萎縮症などがあり、肥満を伴う脂肪肝よりも肝臓の線維化がすすでいたり、肝がんの発生などを含む全体の死亡率が高いなどの報告があります。肥満・非肥満にかかわらず進行する可能性のある脂肪肝は、早くみつけて適正な管理指導を行うことが大変重要です。当院では肝臓の病態をできるだけ正確にお伝えできるよう、肝臓の脂肪量やダメージの蓄積の程度(線維化)を正確に推定できる機能をもった超音波検査での評価を行っております。検診で指摘された肝機能異常は放置せず、いつでもお気軽にご相談ください。